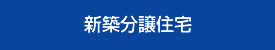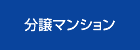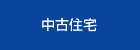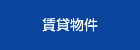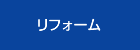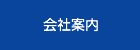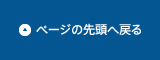電気代の値上がりが続く今、「太陽光発電って本当にお得なの?」「実際、どのくらい電気代を減らせるのだろうか」と、その具体的な節約効果が気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、太陽光発電の仕組みや電気代の削減効果を、シミュレーションや実際の導入事例を交えて紹介。さらに、節約効果を高める工夫や制度のポイントも解説します。
電気を「買う」から「つくる」へと切り替えることで、暮らしがどう変わるのかを見ていきましょう。
太陽光発電の導入で電気代が安くなる!その仕組みとは
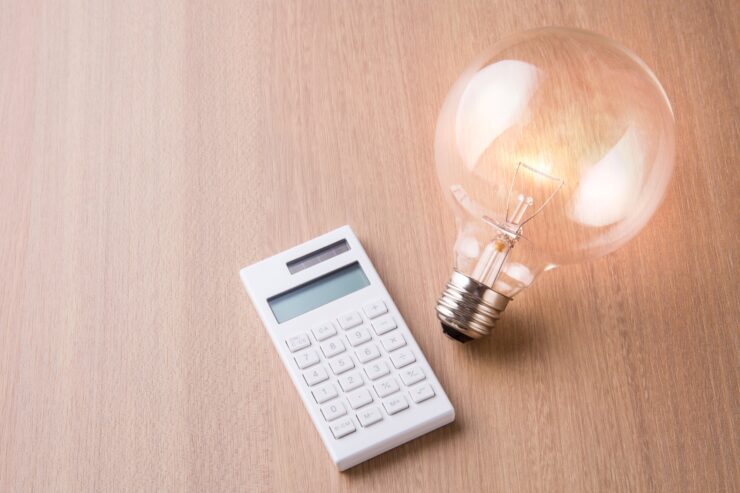
太陽光発電が電気代を安くする仕組みは、非常にシンプルです。 大きく分けると、「①電力会社から買う電気を減らす(自家消費)」と、「②余った電気を電力会社に売る(売電)」という2つのメリットによって、家計の負担を軽減します。
ここでは、それぞれの仕組みを詳しく見ていきましょう。
1. つくった電力を自家消費し、買う電気(支出)を減らす
日中、太陽の光で発電した電力は、照明・冷蔵庫・エアコンなど、家庭内のさまざまな家電に自動的に供給されます。これにより、電力会社から買う電気(買電)の量を直接減らすことができ、月々の電気代を大幅に抑えられます。
例えば、晴れた日の昼間(発電している時間帯)に、消費電力の大きい洗濯乾燥機や食洗機などを稼働させれば、その電力の多くを自家発電でまかなうことが可能です。
さらに、買電量が減れば、電気の使用量に応じて課金される「再エネ賦課金」の支払いも自動的に減るため、二重の節約効果が得られます。
2. 余った電力を売電し、収入を得る
自家消費してもまだ電力が余る場合は、その電力を電力会社に「売る」ことができます(売電)。売った分の電力に応じて、毎月「売電収入」が得られるのが特徴です。
例えば、共働きなどで昼間は不在がち(自家消費が少ない)という家庭でも、発電した電力を無駄にせず、売電によって家計のプラスに変えられます。
この売電収入は、太陽光発電の導入にかかった設備費の回収を早めることにもつながります。
つまり太陽光発電は、「自家消費」によって電力会社への支出(買電量+再エネ賦課金)を減らし、「売電」によって収入を増やすという、2つの大きな理由で電気代の負担を軽減できるエネルギーシステムなのです。
太陽光発電でどれだけ電気代が安くなる?導入家庭の事例とシミュレーション

「太陽光発電で本当に電気代は安くなる?」と気になり、導入を迷う方も多いでしょう。
ここでは、家族構成やライフスタイルの違いによるシミュレーション結果と、実際に導入したご家庭の事例を紹介します。地域ごとの発電効率の違いなど、現実的な目安をつかむための情報に触れていきましょう。
家族構成・ライフスタイル別の電気代削減シミュレーション
太陽光発電でどれくらい電気代が安くなるかは、「発電した電気をどれだけ家の中で使えるか(=自家消費できるか)」で変わります。
この割合を「自家消費率」といい、一般的な住宅ではおおむね30%程度。昼間に家にいる時間が長いほど自家消費率は上がり、節約効果も大きくなります。
4人家族で5kWの太陽光を設置した場合、年間発電量を約5,000kWh、電力会社から買う電気の単価(買電単価)31円/kWh、売電単価を15円/kWhとして計算すると、次のような結果になります。
【自家消費率30%】(共働き夫婦など、平均的な家庭)
(節約額)5,000kWh × 0.3 × 31円 = 46,500円
(売電収入)5,000kWh × 0.7 × 15円 = 52,500円
→年間の経済メリット合計 = 約9万9,000円
【自家消費率50%】(日中の在宅時間が長い家庭)
(節約額)5,000kWh × 0.5 × 31円 = 77,500円
(売電収入)5,000kWh × 0.5 × 15円 = 37,500円
→年間の経済メリット合計 = 約11万5,000円
【自家消費率70%】(在宅時間が長い家庭、かつ蓄電池併用など)
(節約額)5,000kWh × 0.7 × 31円 = 108,500円
(売電収入)5,000kWh × 0.3 × 15円 = 22,500円
→年間の経済メリット合計 = 約13万1,000円
ライフスタイルに合わせて昼間に電気を使う時間を増やす(自家消費率を上げる)だけでも、年間のメリットに大きな差が生まれます。
導入事例に学ぶ電気代の変化
ここからは、ヤング開発で実際に太陽光発電を導入したご家庭のデータをチェックしていきましょう。いずれも2023年の1年間における実績です。
【ケース①】高砂市Y様
家族構成:4人家族(夫・妻パート・9歳・6歳)
太陽光パネル:4.76kW
年間の電気代:126,476円(買電)ー105,441円(売電)=21,035円(支出)
【ケース②】播磨町S様
家族構成:3人家族(夫・妻パート・3歳)
太陽光パネル:5.04kW
年間の電気代:161,636円(買電)ー56,430円(売電)=105,206円(支出)
【ケース③】高砂市W様
家族構成:2人家族(夫・妻・犬1匹)
太陽光パネル:5.04kW
年間の電気代:97,546円(買電)ー109,345円(売電)=-11,799円(黒字!)
3つの世帯の年間電気代は、約10万円の支出から約1万円の黒字と差が大きい結果となりました。
しかし、2人以上世帯における全国平均をみてみると、2023年の年間電気代は147,180円。これに比べれば、いずれの家庭も大幅なコスト削減を実現していることがわかります。
参考:総務省統計局|家計調査報告(家計収支編)2023年(令和5年)平均結果の概要
| ▶太陽光発電システムが無料標準! ヤング開発のその他の無料標準「先進エコ仕様」はこちら |
地域ごとの発電効率・削減効果の違い
太陽光発電の効果は、設置する地域や屋根の向き、天候条件によっても変わります。
例えば、日照時間が長く積雪の少ない太平洋側では年間を通して安定した発電量が見込めるため、有利とされます。
一方で、積雪が多い地域や曇天の多い地域では冬場の発電量が下がる傾向にあり、春から秋にかけての発電を上手に活かす工夫が大切です。
ただし、たとえ日照に有利な地域であっても、「屋根の角度や方角」「周囲に日差しを遮るものがないか」といった個別の設置条件が、発電効率を大きく左右します。
設計段階でこうした地域の気象条件と、自宅の設置条件の両方を踏まえて計画することが、無理なく安定した発電を維持するためのポイントです。
太陽光発電で「電気代ゼロ」に近づくための方法

太陽光発電を導入しても、使い方によって節約効果には差が出ます。発電した電気をできるだけムダなく活用し、買電を減らす工夫をすれば、電気代を「ほぼゼロ」に近づけることも可能です。
ここでは、太陽光発電とあわせて検討したい次の方法を具体的に解説します。
・省エネ機器・家電を導入
・蓄電池やHEMSの活用
・電気料金プランの見直し・最適化
・電気自動車との連携
省エネ機器・家電を導入
太陽光発電を最大限に生かすには、「使う電気そのもの」を減らすことが重要です。住宅全体でエネルギーを効率的に使う仕組みを整えましょう。
例えば、高効率エアコンやヒートポンプ式給湯器(エコキュート)は、少ない電力で大きな効果を発揮します。 特にエコキュートは、電力消費の少ない夜間ではなく、発電している昼間のうちに余った電力でお湯を沸かすよう設定できるため、買電を大幅に削減できます。
また、LED照明や熱交換型の第一種換気システム、消費電力の少ない最新家電(IHクッキングヒーターや食洗機)などを取り入れることも、「使う量そのものを減らす」設計として、結果的に大きな節約につながります。
蓄電池やHEMSの活用
昼間につくった電気を夜間にも使えるようにするのが、家庭用蓄電池の役割です。太陽光発電と組み合わせることで、昼間にためた電力を夜の照明や家電に回し、電力会社からの買電量を大きく減らせます。
電力会社から電気を買えば料金が発生しますが、蓄電池にためた電気は(実質)無料で使えます。電気料金が割高になりがちな夕方から夜間の時間帯を、この蓄電した電力でまかなえるのは、家計にとって大きなプラスです。 また、災害時や停電時にも蓄電池があれば、最低限の電力を確保できるという安心感も得られます。
さらに、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)を併用すれば、家全体の電力使用の「見える化」が可能に。「いつ」「どこで」使っているのかが分かると、自然と省エネ意識が高まり、家族の行動も変わります。
電気料金プランの見直し・最適化
太陽光発電を導入したら、電気料金プランの見直しも忘れずに行いましょう。太陽光発電を導入すると、昼間の買電はほぼゼロになります。さらに蓄電池を併用すれば、夜間の買電も大幅に減らせます。 そのため、これまでの「日中は高いが夜間は安い」といった時間帯別プランが、逆に合わなくなる可能性も出てきます。
自分たちの新しい電気使用パターン(=日中も夜間もほとんど電気を買わない)に合わせた最適なプランを検討しましょう。電力会社によっては太陽光・蓄電池導入家庭向けに、再エネ応援プランやポイント還元を実施しているケースも。契約内容を見直すだけで、長期的な節約効果が得られます。
電気自動車との連携
太陽光発電でつくった電気を、移動のエネルギーとして活用する家庭も増えています。
電気自動車(EV)を自宅で充電すれば、発電した電気をそのまま車に蓄え、日常の通勤や買い物に使えます。これにより、ガソリン代の負担を丸ごと削減できます。
さらに、V2H(Vehicle to Home)の仕組みを取り入れれば、EVを「走る蓄電池」として活用できます。 家庭用蓄電池と同様に、EVに蓄えられた大容量の電力を夜間の生活電力として使えるため、買電をさらに減らせるだけでなく、災害時の強力なバックアップ電源にもなるのです。
「昼に発電し、蓄えた電力を夜間の生活や車の移動で使う」というエネルギーの循環により、家計の負担減と環境への配慮を両立できる住まいが実現します。
太陽光発電の売電収入に関する制度と平均額

太陽光発電は、つくった電気を自宅で使うだけでなく、余った分を電力会社に売ることもできます。
毎月の請求書に「買電」と「売電」の両方が並び、季節によっては支払いより売電額が上回ることもあります。
家計の「もうひとつの収入源」として、実際にどのくらいの金額になるのかをみてみましょう。
FIT制度(固定価格買取制度)とは
住宅用の太陽光発電(10kW未満)では、「FIT(固定価格買取制度)」が適用されます。
これは、発電した電気のうち、余った分(余剰電力)を電力会社が10年間、国が定めた固定価格で買い取ることを約束する制度です。契約期間中は価格が変わらないため、家計の収益見込みを計算しやすいのが特徴です。
2025年度上半期(4~9月)に認定された住宅用太陽光の買取価格は1kWhあたり15円。そして2025年10月からは制度が見直され、設置後の年数に応じて価格が変わる新しい仕組みが始まっています。導入から4年間は1kWhあたり24円、5年目以降は8.3円での買取が適用される二段階制となりました。
FIT制度は今後も段階的な見直しが予定されており、設置時期によって条件が変わる可能性があります。太陽光発電を検討する際は、最新の買取価格と制度内容を確認したうえで収支をシミュレーションしましょう。
参考:経済産業省資源エネルギー庁|FIT・FIP制度 買取価格・期間等(2025年度以降)
年間の平均売電額と今後の見通し
住宅に5kW程度の太陽光パネルを設置した場合、年間の発電量はおよそ5,000〜6,000kWhが目安です。仮に、そのうち半分(2,500kWh)を売電すると、導入から4年間は1年あたり約6万円(2,500kWh × 24円/kWh)の売電収入が見込めます。
春や秋など日照時間が安定する季節には発電量が増え、月によっては電気代の支払いより売電額が上回ることもあります。
ただし、この売電単価(2025年度以降:8.3~24円)は、電力会社から電気を買う単価(買電単価:30円以上)と比べて、非常に安くなっています。
これが、「売る」より「使う(自家消費する)」ほうが圧倒的に得になる現在の状況です。つまり、 24円で売るよりも、31円で買うはずだった電気を自家発電でまかなう(=31円節約する)方が、経済的なメリットが大きくなるというわけです。
日中に家電を稼働させたり、電気自動車の充電に活用したりするなど、発電した電力を生活の中で最大限に活かすことが大切です。さらに、蓄電池を併用すれば夜間の買電を減らせるため、光熱費ゼロも現実的な目標になります。
売電は、制度初期のような「儲けるための仕組み」から、電気代高騰から「家計を守るための仕組み」へ。これが、太陽光発電の現在の姿といえるでしょう。
まとめ|ヤング開発は太陽光発電が全戸無料標準!

太陽光発電は、光熱費を抑えながら、エネルギーを自給できるこれからの暮らしに欠かせない仕組みです。
日中の電気を自分の家でまかなえるだけでなく、余った電気を売って家計の支えにできる点も大きな魅力です。
省エネ家電や蓄電池を組み合わせれば、電気代をほとんど払わない暮らしも夢ではありません。
これからマイホームを検討するなら、家のデザインや間取りだけでなく、暮らしのランニングコストにもぜひ目を向けてみてくださいね。
その「ランニングコスト」の課題に応えるため、兵庫で家づくりを行うヤング開発では、記事でご紹介した太陽光発電を全戸に無料で標準搭載しています。さらに、断熱等性能等級6(HEAT20 G2相当)の断熱性能や、一次エネルギー消費量35%以上削減といった「GX志向型住宅」基準を満たす高性能な住まいを標準仕様としています。
ヤング開発の「標準仕様」が、光熱費をどれだけ抑えながら快適な暮らしを実現するのか、ぜひモデルハウスでご体感ください。また、太陽光発電や省エネ住宅の仕組みを詳しく知りたい方は、お電話やお問い合わせフォームからお気軽にご相談いただけます。「未来まで安心できる」を、ヤング開発がご提案します。
| ▶太陽光発電システムが無料標準! ヤング開発のその他の無料標準「先進エコ仕様」はこちら |
2026年2月 (9)
2026年1月 (10)
2025年12月 (10)
2025年11月 (10)
2025年10月 (10)
2025年9月 (10)
2025年8月 (10)
2025年7月 (10)
2025年6月 (10)
2025年5月 (10)
2025年4月 (8)
2025年3月 (8)
2025年2月 (11)
2025年1月 (9)
2024年12月 (11)
2024年11月 (9)
2024年10月 (10)
2024年9月 (8)
2024年8月 (10)
2024年7月 (9)
2024年6月 (11)
2024年5月 (19)
2024年4月 (9)
2024年3月 (8)
2024年2月 (7)
2024年1月 (9)
2023年12月 (9)
2023年11月 (8)
2023年10月 (10)
2023年9月 (10)
2023年8月 (8)
2023年7月 (8)
2023年6月 (10)
2023年5月 (7)
2023年4月 (9)
2023年3月 (9)
2023年2月 (9)
2023年1月 (8)
2022年12月 (11)
2022年11月 (8)
2022年10月 (8)
2022年9月 (8)
2022年8月 (7)
2022年7月 (8)
2022年6月 (7)
2022年5月 (8)
2022年4月 (8)
2022年3月 (8)
2022年2月 (8)
2022年1月 (8)
2021年12月 (8)
2021年11月 (7)
2021年10月 (7)
2021年9月 (8)
2021年8月 (8)
2021年7月 (8)
2021年6月 (8)
2021年5月 (8)
2021年4月 (8)
2021年3月 (7)
2021年2月 (8)
2021年1月 (8)
2020年12月 (8)
2020年11月 (8)
2020年10月 (7)
2020年9月 (8)
2020年8月 (8)
2020年7月 (8)
2020年6月 (8)
2020年5月 (9)
2020年4月 (8)
2020年3月 (8)
2020年2月 (8)
2020年1月 (8)
2019年12月 (8)
2019年11月 (8)
2019年10月 (8)
2019年9月 (8)
2019年8月 (8)
2019年7月 (8)
2019年6月 (8)
2019年5月 (8)
2019年4月 (8)
2019年3月 (8)
2019年2月 (8)
2019年1月 (8)
2018年12月 (7)