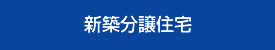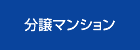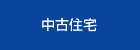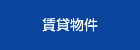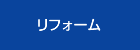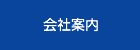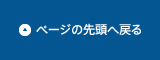台風シーズンになると、「うちは大丈夫だろうか…」と不安になる方も多いのではないでしょうか。新しくマイホームを建てるとなればなおさら、台風や豪雨にも強い、安心して暮らせる住まいにしたいものです。
この記事では、「台風に強い家」を建てるために押さえておきたい災害対策のポイントを分かりやすく解説します。立地や地盤、構造、外装や開口部のポイントから、停電・断水時のライフライン対策まで、今後の家づくりに必ず役立つ情報をまとめました。
家づくりを検討している方はもちろん、台風対策の見直しを考えている方もぜひ参考にしてください。
深刻化する台風・豪雨災害~住まいに与える影響とは~
近年、地球温暖化による影響もあり、台風や豪雨が強まる傾向にあります。ニュースなどで住宅被害の報道を目にすると不安を感じることもあるかもしれませんが、家づくりの段階から適切な対策を講じておけば、安心・安全な暮らしを実現できます。
土地選びや地盤調査、建物の構造や基礎の設計、外装や開口部の仕様など、防災性能の高い家づくりを意識することで、将来的なリスクや出費を最小限に抑えられるのです。新築時の備えが、長い目で見て家族の安全と快適な生活を守るカギとなります。
台風や豪雨が住まいにもたらす被害とは
ここからは、台風や豪雨が住まいにもたらす主な2つの被害、「風害」「水害」について解説します。
【風害】

風速は10m/s程度から「強風」と認識されるレベルとなりますが、「強い台風」と発表されている場合の最大風速は33~43 m/sと、「立っていられない」レベルの強風が吹くこともあります。大きな被害をもたらした令和元年の東日本台風では、最大風速44.8 m/sが観測されました。
台風による暴風は、屋根材や外壁材を吹き飛ばしたり、飛来物によって建物や窓ガラスを破損させたりする恐れがあります。しかしこうしたリスクは、構造体や外装を強化する「耐風対策」により、損傷リスクを大きく減らせます。
【水害】

台風では、大雨による水害も大きなリスクとなります。令和元年の東日本台風では暴風に加えて豪雨も発生し、最大値942.5mmの記録的な大雨が観測されました。さらに近年は、特定の地域に急激な大雨をもたらす「線状降水帯」も頻発しています。
こうした大雨は、床下・床上浸水や河川の氾濫、内水氾濫につながることがあります。沿岸部や低地では、台風の影響による「高潮」や「高波」により海水が住宅地に流れ込むことも考えられるでしょう。また、山間部や傾斜地では、土砂崩れや土石流の発生にも注意が必要です。
ただし、これらの水害リスクは、ハザードマップの確認や土地選び、適切な排水計画や防水対策など、新築時の備えによってリスクを軽減できます。
新築時に検討したい!台風に強い家にするためのポイント

台風に強い家を建てるために、具体的にはどんな点に注意すればいいのでしょうか。ここからは、家づくりのポイントについて詳しく解説していきます。
立地・地盤でリスクを減らす
【ハザードマップで洪水・高潮・土砂災害リスクを確認】
家を建てる前に、その土地がどのような災害リスクにさらされているかを把握しましょう。
各自治体が公開しているハザードマップを活用すると、洪水や高潮、土砂災害の危険箇所を確認できます。詳しくチェックしてみると、意外にも住宅地の一部が過去の浸水範囲や土砂災害警戒区域に該当していることも。
新築を計画する際は、必ずハザードマップで土地の安全性を見極め、できる限りリスクの低い場所を選びましょう。不動産会社や建築会社にも、念のため確認を依頼してください。
【地盤調査と地盤改良】

地盤の強さや性質も住まいの安全性を大きく左右します。
軟弱地盤や盛土の土地は、豪雨時に地盤沈下や土砂崩れを引き起こすリスクがあります。新築工事の際には必ず地盤調査を行い、必要に応じて地盤改良工事を実施することが大切です。
地盤改良には、表層改良や柱状改良、鋼管杭などさまざまな方法があるため、専門家と相談しながら最適な工法を選びましょう。
| ▶全戸無料で地盤調査・地盤改良を実施! ヤング開発の安心・確実な施工体制について、詳しくはこちら |
基礎・構造で耐風・耐水性を高める
【耐風等級と耐震等級】
家づくりでは、地震に対する強さを示す「耐震等級」が重視されますが、実は「耐風等級」も重要なチェックポイントです。
耐風等級は、風圧に対する住宅の崩壊・倒壊・損傷のしにくさをあらわすもので、耐震等級と同じく「住宅性能表示制度」により定められている指標です。
建築基準法では、強風に耐えられる構造とすることが義務付けられていますが、より安全を追求するなら「耐風等級2」や「耐震等級3」といった、高い基準で設計することをおすすめします。
【風を受け流す建物形状、低重心設計】

建物の形状や高さも、台風の強風に対する耐性に大きく関わります。
屋根や壁の凹凸が少ないシンプルな形状、または平屋や総2階建てのような低重心の建物は、風を受け流しやすく、被害を抑える効果が期待できます。
見た目のデザインも大切ですが、安全性という観点からも形状を検討してみましょう。
【基礎の高さ設定で浸水対策】
基礎を通常よりも10~30cm高くする「高基礎」にすれば、床下・床上浸水のリスクを軽減できます。万が一雨水が入り込んだ際も床下のメンテナンスがしやすく、通気が良いため構造の腐食やシロアリを防げるメリットもあります。
台風や豪雨のリスクが高い地域では、基礎の仕様についてもしっかり打ち合わせをしておきましょう。
屋根・外壁で家を守る
【飛散しにくい屋根材】
屋根は、台風による被害をもっとも受けやすい部分です。
台風被害を防ぐためには、風圧に強い「防災瓦」、耐久性・耐食性・防水性に優れた「ガルバリウム鋼板」などがおすすめです。どちらもビスや釘を用いて下地にしっかり固定される点が特徴で、強風や豪雨が発生してもズレたり飛散したりする心配がありません。
屋根材は風への強さや耐久性も重視して選びましょう。
【耐久性・耐水性の高い外壁】

耐久性や耐水性が高い外壁材として、サイディングやタイルなどが挙げられますが、一般的に普及している外壁材であれば、台風時の雨漏りなどを心配する必要はありません。
それよりも重要なのは、シーリングや防水シートなど細部の納まりです。新築時には、これらの部分が適切に施工されているか細かくチェックし、完成後も定期的なメンテナンスを欠かさず行うことで、台風や豪雨から住まいをしっかり守ることができます。
開口部の防護を強化する
【耐風圧・高水密サッシの採用】
台風時には、強い風が窓ガラスをあおったり、隙間から雨水が吹き込むことが問題となりますが、近年の住宅用サッシは耐風圧や気密・水密性が大幅に向上しています。
台風対策をさらに強化する場合は、JIS(日本工業規格)の「耐風圧性能」や「水密性能」の等級が高いものを選ぶことで、ガラスの破損や浸水リスクを大きく減らせるでしょう。
【シャッターや雨戸の設置】

万が一の飛来物対策や、防犯も兼ねて、窓にはシャッターや雨戸を設置することをおすすめします。最近は電動シャッターや通風雨戸など、使い勝手にも配慮した製品が増えています。
「窓ガラスが割れたらどうしよう…」という心配を減らし、安心して台風をやり過ごすためにも、開口部の備えは万全にしておきましょう。
排水・雨水対策を取り入れる
【屋外排水設備の整備】
敷地内の水はけが悪いと、短時間の豪雨でも家の周りに水が溜まりやすくなり、床下浸水や基礎へのダメージにつながります。
新築時には、雨どいや集水桝などの排水設備を十分に整備することが基本です。排水の流れを適切に設計し、定期的に掃除やメンテナンスを行うことで、トラブルを未然に防げます。
【止水板や逆流防止装置の活用】
雨水や下水の流入を防ぐために、玄関や勝手口に止水板を設置すると安心です。また、トイレや排水口に「逆流防止装置」を取り付けておくと、下水の逆流による室内浸水を防ぐことができます。
これらのアイテムは一見地味ですが、万が一の時に大きな安心につながります。特に都市部や低地では、急激な大雨の際に排水路が溢れやすくなるため、事前の備えを徹底しましょう。
停電・断水へ備える
【太陽光発電+蓄電池の導入】

もしもの停電に備え、太陽光発電と蓄電池システムを設置しておくと安心です。自家発電と蓄電で、照明や冷蔵庫など最低限の生活インフラを維持できます。
夜間や荒天時でも電気が使えれば、非常に心強く感じるでしょう。
【非常用電源の確保】
太陽光発電が難しい場合でも、ポータブル電源や発電機の準備があると、停電時の不安を大幅に減らせます。スマートフォンの充電、電気ポットやラジオの稼働など、「いざ」というときのために、あらかじめ使い方を確認しておきましょう。
その他の台風対策ポイント

台風や豪雨に強い家にするためには、保険やメンテナンスも重要なポイントです。いざという時のリスクを軽減し、暮らしの安心につながります。
保険(火災保険・水災補償)の選び方
万が一の災害で経済的なダメージを最小限に抑えるためには、保険による備えも大切です。
火災保険を契約する際は、台風や豪雨による水災補償がしっかり含まれているか、内容を確認しましょう。特に浸水や土砂災害が懸念される地域では、水災オプションの加入を検討することをおすすめします。
補助制度・助成金の活用
自治体によっては、耐震・耐風・浸水対策など、住宅の防災強化のための補助金や助成金制度を設けている場合があります。
たとえば、建て替えの際の盛土工事や止水板の設置、蓄電池や非常用電源の導入などが対象となり、条件を満たせば費用の一部を支援してもらえることがあります。新築を計画する際は、まず自治体のホームページで最新情報をチェックしてみましょう。不明な点は住宅会社に相談するとスムーズです。
定期的なメンテナンスで性能を維持
どんなに性能の高い家でも、経年による傷みや劣化は避けられません。屋根や外壁、サッシ、排水設備などは、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。
家づくりの際は、建てたあとも安心して暮らせるよう、アフターサービスが手厚い住宅会社を選ぶようにしましょう。新築時の高い性能を長く保つことにもつながります。
まとめ| 「台風に強い家」で、安心・安全な暮らしをつくる

台風や豪雨に強い家をつくるには、土地選びから構造、開口部や外構まで、多角的な対策が欠かせません。新築時にしっかり備えておけば、万が一の災害時も家族の安全と住まいの資産価値を守ることができます。
将来の安心を手に入れるためにも、今回紹介した内容を参考に、家づくりや防災対策を見直してみてください。
ヤング開発の「強固な家創り」
ヤング開発では、長年にわたり「安心・安全な住まいづくり」に取り組んできました。従来の木造軸組工法にヤング開発独自の技術を導入し、災害に負けない「強固な家創り」を実現しています。
・全戸無料の地盤調査・地盤改良
・地震や暴風にも負けない構造をつくる「SHMB工法」
・耐久性・耐水性に優れた屋根・外壁
・長期出力保証付きの太陽光発電システム
さらに、最高等級である「耐風等級2」「耐震等級3」を取得可能!
兵庫県(神戸・明石・加古川・高砂・姫路)エリアで「台風に強い家を建てたい」とお考えの方は、お気軽にご相談ください。
| ▶台風や豪雨、自然災害に負けない強い家を実現! ヤング開発の「強固な家創り」についてはこちら |
2025年12月 (3)
2025年11月 (10)
2025年10月 (10)
2025年9月 (10)
2025年8月 (10)
2025年7月 (10)
2025年6月 (10)
2025年5月 (10)
2025年4月 (9)
2025年3月 (8)
2025年2月 (11)
2025年1月 (9)
2024年12月 (11)
2024年11月 (9)
2024年10月 (10)
2024年9月 (9)
2024年8月 (10)
2024年7月 (9)
2024年6月 (11)
2024年5月 (20)
2024年4月 (9)
2024年3月 (8)
2024年2月 (7)
2024年1月 (9)
2023年12月 (9)
2023年11月 (8)
2023年10月 (10)
2023年9月 (10)
2023年8月 (8)
2023年7月 (8)
2023年6月 (10)
2023年5月 (7)
2023年4月 (9)
2023年3月 (9)
2023年2月 (9)
2023年1月 (8)
2022年12月 (11)
2022年11月 (8)
2022年10月 (8)
2022年9月 (8)
2022年8月 (7)
2022年7月 (8)
2022年6月 (7)
2022年5月 (8)
2022年4月 (8)
2022年3月 (8)
2022年2月 (8)
2022年1月 (8)
2021年12月 (8)
2021年11月 (7)
2021年10月 (7)
2021年9月 (8)
2021年8月 (8)
2021年7月 (8)
2021年6月 (8)
2021年5月 (8)
2021年4月 (8)
2021年3月 (7)
2021年2月 (8)
2021年1月 (8)
2020年12月 (8)
2020年11月 (8)
2020年10月 (7)
2020年9月 (8)
2020年8月 (8)
2020年7月 (8)
2020年6月 (8)
2020年5月 (9)
2020年4月 (8)
2020年3月 (8)
2020年2月 (8)
2020年1月 (8)
2019年12月 (8)
2019年11月 (8)
2019年10月 (8)
2019年9月 (8)
2019年8月 (8)
2019年7月 (8)
2019年6月 (8)
2019年5月 (8)
2019年4月 (8)
2019年3月 (8)
2019年2月 (8)
2019年1月 (8)
2018年12月 (7)